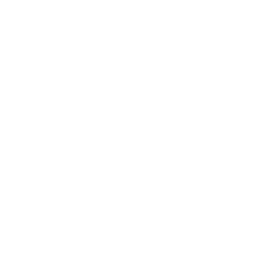
ライフビジョン学会と
ユニオンアカデミー会員による
■年報「あかでめいあ」
特集:平和の畑を耕す集い:より■
「過去と真摯に向きあうのは迂遠な課題だとして、時流はその愚直さを軽蔑するが、その結果が現代の荒廃ではないか。そう思うので老人の体験を幾つか並べてみたい。」(本文より)
戦争を語れる人が少なくなった。歴史を学ばない世代は都合のよい材料をつまみ食いして、加害の過去を隠蔽しようとしている。
自国に愛情とプライドを持つために、戦争を直接知る皆様の記録を残したい。(編集部) |
|
「団塊の世代」論議から
二月の連休にNHKテレビが団塊の世代についての特集番組を放映した。ボランティア仲間のYさんの感想を聞いた。団塊の世代の一員である彼女は、当事者として受け止めたようで猛烈に腹がたったという。「上の世代も若い世代もわたし達に集中砲火を浴びせるが、それは違う。わたし達はしっかり働いてきたし、社会的にも戦ってきた自負がある」と。団塊世代の親たちに近い私は、この討論の冒頭に登場した三〇代の青年の「団塊の世代は戦後教育の一番悪いところで育ったから」駄目だという発言に、多分Yさん以上に腹をたて、もうそのあとは見なかった。
この若者はかねてから、戦後教育は間違っていたのに、それを自覚せずに高度成長を謳歌した団塊世代は、糾弾すべき存在と考えているのだろう。若い世代が先行する世代を批判するのは、何時の時代にもあったことでそれ自体は不思議ではない。しかし戦後という言葉にこめられた歴史性への洞察がないならば、その批判は天に唾するだけだろう。
過去と真摯に向きあうのは迂遠な課題だとして、時流はその愚直さを軽蔑するが、その結果が現代の荒廃ではないか。そう思うので老人の体験を幾つか並べてみたい。
戊辰戦争という内戦の記憶
私は九州鹿児島の出身である。十四歳で陸軍幼年学校に入るために郷土と別れ、もう一度青年時代の十年を郷里で過ごして東京へ出てきた。それから半世紀以上たつ。育った親の土地は他人に渡り、鹿児島人という意識も殆ど忘れて過ごしてきた。
同期生に佐賀出身のTという仲良しがいて、これが町工場を経営していた。会津に取引先があってよく行き来していた。あるとき、会津はいいところだから一緒に行かないかと誘ってくれた。その時のことである。出掛けにTがいう。「おい、会津についたら生まれが鹿児島と言うなよ。会津の人は戊辰戦争の怨みを絶対に忘れていないから」
それまで私は福島の人達の深層意識を知らなかった。薩長の官軍が東北諸藩を征討する内戦をへて明治維新は成就したわけだが、そのあと東北の人士がどれだけ冷遇されたか、薩閥出身の官僚が東北や北海道でどれだけ暴政を敷いたか、私も学ばなかったわけではない。義憤を感じたこともある。しかしその重さはTにいわれて始めて実感した。
それから私は意識して戊辰戦争への東北人の発言に気をつけるようになった。鹿児島・山口県人以外の第三者の評価も聞いた。征服者である長州の大官が会津藩の武家の娘と房事におよび、その最中に下から刺されて死んだ事件も、この会津旅行以後に知った。戊辰戦争から百数十年たっている。その後の日本には日清日露の両大戦を始めとする幾つもの国民的記憶がある。会津ではそれより深いとところに今でも戊辰戦争が刻印されている。こういう深層の記憶は会津だけだろうか。日本全体が外国との関係を考える時にもヒントになるのではなかろうか。
従軍慰安婦についての記憶
歴史教科書を書き換えたがっている自民党のタカ派が、従軍慰安婦の存在を否定したくてこれまでの政府見解の見直しまでいい始めている。
私の手元に「アジア女性基金〜『従軍慰安婦』にされた方々への償いのために」という小冊子がある。発行日は一九九五年十月二十五日、発行者は「女性のためのアジア平和国民基金」理事長 原文兵衛(元警視総監/参議院議長)。この基金は戦後五十年の節目に時の村山富一総理が、従軍慰安婦とされた人達へのお詫びと償いの気持を表すために作った。その発足には複雑な政治力学が潜んでいたようだ。国家としての責任を認めたくない日本政府も道義的責任は否定できなかったから、社会党首班の好機にある種の妥協を成立させて、第三セクターのような組織が作られたというべきか。
この基金にはできた時から左右両派から厳しい批判があった。右からの批判は国の関与や強制はなかった、謝罪の必要なしというものである。近頃の反発もその繰返しだ。形式論はあるが苦しめられた人達への人間感情はない。左からの批判は、政府の公式謝罪で国家の責任を明らかにすべしとの原則論で、年老いた当事者への支援は視野にない。
基金は従軍慰安婦だった人達に村山富一、続いて橋本龍太郎という総理名義の親書と、可能な限りの補償金を届けた。その償い事業は昨年終了した。償いの原資は国民的な募金により、最終的に五億五千万は拠出された筈である。事務経費は国が負担し、先にふれた総理挨拶も役所の文書とすれば珍しく心のこもったものだった。与党の右派はこの事業を黙殺し、現在ではあからさまに否定しようとしている。歴史修正派の一員でもある現総理が当時の官房長官談話を継承するというのは、諸外国からの批判にこれを免罪符に利用したい打算のゆえだろう。
私がこの冊子を持っているのは基金から送って貰ったからである。基金が発足する少し前、私は幼年学校からの親友でその三年前に死んだ I の追悼録を編纂した。殆ど費用をかけなかったのにI夫人は思いがけない金額の謝礼を送ってきた。軍人のありかたや愛国心のことを一番深く論じ合った友であったIを思い、彼ならこの基金について何というだろうかと考えた。敬虔なクリスチャンだったIも国の責任が第一といったかもしれない。しかし当時の帝国陸軍に縁あった者として、我々の軍隊が苦しめた人達への最低限の責任感を表すことには同意するに違いない。そう思ったから、夫人に頂いたお金の大部分をこの基金へカンパした。それが私の名前も基金に登録された所以である。
従軍慰安婦のことで知ってほしいことがある。『修羅の翼/零戦特攻隊員の真情』という戦記本がある。著者は十五歳で海軍航空に身を投じ、少年兵から叩き上げて終戦時は二十六歳のベテラン戦闘機乗りとして辛くも生き残った角田和男という海軍中尉である。ラバウルやレイテ、硫黄島、沖縄と命を的の空中戦での日常が淡々として描かれている。もちろん反戦文学ではないが過剰な戦争賛美でもない。使命のままに死んでいった戦友・上官・部下への鎮魂記である。筆者の人柄だろうが周囲の人達への悪口が滅多に出てこないのは、こういう戦記では珍しい叙述である。この中に何カ所か従軍慰安婦についての記事があるが、その一節。
「ラバウルにいる海軍下士官兵用の慰安婦は北朝鮮出身者が多いのだが、始めは女子勤労挺身隊として徴用され、横濱に着いた時に内地の軍需工場と前線の慰安部隊との希望を聞かれ、気の強い仲間が仕事の内容は知らずに、お茶汲みか食事洗濯の手伝いぐらいに考えて前線を志望した。船に乗せられトラック島へ向かう途中で、初めて慰安婦の仕事を説明され驚いたが既に遅かった。監督の説明では、もし万一ここで戦死するようなことがあれば、身分を一階級進めて特旨看護婦として公表され、靖国神社に祭ってもらえるとの事だった(一部略)」とある。
官憲による強制の証拠がないからといって、彼女らの存在を任意といえるものだろうか。当時を生きた人ならみな知っているが徴用とは招集と同じ強制だった。その上で甘言を弄して騙している。これは給養がよかった海軍の、中でも比較的に自由と自律が許されていた航空隊搭乗員が書き残した事だが、一つの慰安所に何十人もの兵隊が並び、「早くしろ」という怒鳴り声の中で、次から次へと相手させられたという中国戦線での状況など聞き及ぶと、女性への人権蹂躙と咎められるのは当然ではないか。そういう事業を軍の経理部が管理していた、すなわち国の関与を日本政府は一旦認めたのである。
角田さんは先の文章に続けて「もしここで敵襲があり命を落とすのなら、彼女らと一緒にいてやろう」と決心しているが、自国の承認をとりけし謝罪はしないと開き直る現代の政治家たちには、この戦闘機乗りの優しさも自虐史観に見えるのだろうか。
ある同期生Yの記憶
五年ほど前、同期生の有志十人ほどで箱根に旅行したことがある。戦後半世紀以上すぎていたが、別の学班(普通教科のクラス)だったYと始めて再会した。その時、Yに聞かれた。
「卒業の直前に海軍の爆撃機が不時着したのを覚えているか」
あれは九六式の攻撃機だった。学校の北に落ちた。それは私もよく覚えている。学校当局がすぐ救援に向い、搭乗員のクルーは数日われわれの生徒舎に宿泊した。
Yはさらにこう言った。「あの時、話に行った連中がいたが、君は行かなかったか」
「いや、それは知らない」
YによればYを含む何人かで搭乗員の話を聞いた。その時、一緒だった奴を思い出してその内容を再確認したいのだと。Yの記憶は次のようなものだった。
「あの航空隊員たちが戦場の話をした。自分たちの経験か、君たち陸軍がやっていることと言ったのかそれは今定かでないが、中国の戦線で、赤んぼをつかまえて空中に放り上げる。落ちてくるところに銃剣を突きたてておいて串刺しにする。そんな事をして兵隊が遊んでいる。そういう内容だった。誰かがそれを日記に書いたらしく、(生徒は毎日毛筆で日記を書くことになっており、定期的に武官の教官の検閲を受けた)そのあと週番士官から海軍のいる部屋への立ち入りを禁止された」
始めて聞く話だった。Yは確かにそう聞いたのだが、誰に尋ねても覚えている奴がいないと嘆いていた。Yは大手の造船所の設計技師をしていた人で、労働組合や平和運動には関係ない。この会合の暫くのち癌のため他界したが、この記憶を生涯忘れられなかったのだろう。本気で打ち明けたのは私だけだったかもしれない。恐ろしい話である。だが報道や法律論では日時場所も特定されていないデマとして否定されるだろう。
その論理で南京虐殺事件での百人斬り競争もなかったという言説がふりまかれた。それを据物斬りと報道した本多勝一記者と新聞社は名誉棄損で訴えられた。しかし東京地裁はこの請求を却下し、昨年末には最高裁で本多側の勝訴で決着した。
この報道と訴訟の過程では、私の小学生時代の記憶が白黒を決するキーワードとなっていた。それはあるミニコミ誌に発表した敵兵を斬った本人の講話を再現した文章だった。南京事件否定派は少年の記憶は信用できない、他に聞いた人はいないなどと反論したが、事実を追認する同級生の手紙もあり、南京事件そのものについて膨大な未発表資料が発掘されたこともあって、裁判所は(私の文も)一概に虚偽といえないと認定した。
Yの記憶は証拠としてはそれより弱いかもしれないが、戦時中に軍隊の一角でこういう話が語られていたこと自体に重みがある。このような噂話の類にこそ真実が潜んでいるのが、世間というものであると思う。それは会津人の奥深い県民感情とも通底しているのではなかろうか。
戦争に直接参加した世代はどんどん死んでいく。映画になる時は、特攻隊とか戦艦大和とか硫黄島とか、日本がどん詰まりにきて国土防衛という心情が成り立ちえた戦場や作戦の話ばかりが若い人達に伝えられていく。
例えばニューギニアへの第十八軍十四万のうち生還は僅か一万三千、死者の大部分は密林の中で餓死したというような事は映画にならない。そして、よそ様に攻め込んだ加害の体験を心の奥で悔やんでいた兵士たちは、その痛みゆえに地獄の底まで口を閉ざしてあの世へ行く。最近はそこにつけこんだ新手の特攻映画まで現れる。
わが兄たちは傲慢な知事を讃えるために命を捧げたのではない。特攻隊のことを考えるなら、感動するよりも無謀な命令をだした責任の所在を論ずるのが政治家の務めではないか。これが日本国が荒んでいく本当の原因である。過労死を自己責任にする経営思想と戦争責任のすり替えは、同じ根からでていると私は思っている。
東洋平和のためという記憶
今年は日中戦争七〇周年である。右翼の雑誌がその記念特集を組んでいるのには呆れるが、それはさておく。
七・七事変が始まった時、私は小学校四年生だった。本家の従兄弟二人が招集されたこともあって、出征兵士を送る行事には一生懸命参加した。電車通りに並んで日の丸の小旗を打ち振ったことなど昨日のように思い出す。その昂揚の中で「勝って来るぞと勇ましく」(露営の歌)と熱唱すれば、兵隊と市民と子どもは一体となった。この歌の最終句は「東洋平和のためならば何で命が惜しかろか」というもので、少年の私達はここから戦争の大義を受け取った。私達が「忠勇無双のわが兵は」と歌っていた時、敵国にも同様な忠勇無双の兵士がいて、しかもその背後には我々と同じような普通の庶民や子どもがいることには全く思い至らなかった。それが何を齎すかを知るのは、空襲や食料難や兄や従兄弟の戦死などなどを体験してからである。いままた似たようなスローガンが溢れているのをみると、私には今は戦前のように思えてならない。
「親の因果が子に報い」という。父祖の責任は個人を越えて後の世代全体に引き継がれる。戦争体験者はまだいる筈である。自分のため、家族のため、国のため、若者たちに事実を学んでほしいと思う。これから択ぶべき道が見えて来るだろうから。
ここまで書いてきて昭和天皇の戦時中の肉声なるものを新聞で読んだ。最近の歴史修正主義者たちは、裕仁天皇の痛恨をも踏みにじろうとしているのだろうか。
(二〇〇七年三月一〇日記)
【参考資料】
☆『修羅の翼 零戦特攻隊員の真情』今日の話題社/角田和男
☆岩波書店『世界』二〇〇五年十一月号/熊谷伸一郎論文「南京事件百人斬り訴訟」
☆『天皇の軍隊』小学館/大江志之夫
☆『天皇の軍隊と日中戦争』大月書店/藤原彰
☆『南京大虐殺否定論13のウソ』柏書房/本多勝一・藤原彰ほか
|