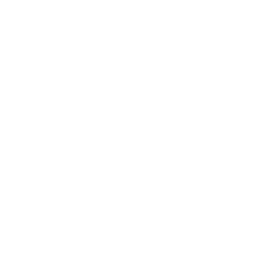
 ������œ����d�@�N���B
�d���̃v���̓��[���A�������� 
���̌��e�͉����X�쒘�E�J���g������2�@�J�����ԂƂ͉����\�\�u���������v�͖{�����H��蔲�����ďЉ�܂��B
|
|
�@���ς�炸�J�����ԂɊւ����Ȃ��b���������Ă���B���Ɉ��̓��j�������x��ł��Ȃ��j���Ј��A�����̎q���̉^����̋x�݂����Ȃ��̂Ő��E������p�[�g�ɂȂ낤�Ƃ��Ă��鏗���ۈ�m�A�J�����ԊǗ����S���Ȃ���Ă��Ȃ��̔��E�A�J��̍��@�ɔ����ĉR�̏��ނ���������Ǘ��E�B
�@�ނ�͂Ȃ������Ȃ��B�u�d���������Ȃ��̂ɕ���Ȃ������瓭���Ȃ��Ȃ����Ⴄ�v����B�d�����Ȃ�������������œ����A�������璷���ԓ����B���̂����J�����ԊǗ��͂��邸��ɂȂ�A�E��ɂ͒����������Ƃ������S�݂̏����ȕ��͋C���ł���B
�@�Εׂȓ����a�͎���̎d���̎�l���ł���B�ΕׂƂ͓����I�ɖڕW���f���Ă��̎����Ɉꏊ�����ɂȂ邱�Ƃł���B�����邽�߂����̓����a�݂͂��߂ł���B
�@��������l���ɂȂ�l���̂��߂ɁA�����ԘJ������߂悤�B�d���ʂ��V�F�A���ĐV���Ȍٗp�𑝂₻���B��l��l�̓�������ς��āA�l�̐l���ƎЉ�ɗǂ��z�������炻���B
�J�����ԂƂ͉����\�\�u���������v�͖{�����H
�����X��
�����ԘJ�����Ε�
�@���j�̖{�ɂ����[�}�l�͂قƂ�njl���Y�ɂ�����炸�A�l�̏Z���Ȃǂɂ͂��܂�S�Ȃ��A���Ⴟ�ȉƂɏZ��łЂ�����퓬�ɗ�������B�����đs��Ȍ����{�݂��������ꂽ�̂ł���B�n���������ĔY�ނȂ�Ă��Ƃ͂Ȃ������̂ł��낤�B���̌��ʂ��働�[�}�鍑�ł���B��������퓬�s�ׂɗ�߂Ȃǂƌ����̂ł͂Ȃ��B���[�}�s���ɂ͂��ꂪ���Ƃł������B
�@���{�l�͂��āu�����������ɏZ�ޓ������Łv�ƌ���ꂽ���Ƃ�����B���s�ȓ@��͊m���ɉ��K�ł��낤���A�킪���y�͋����B��Ƒ��͏��Ȃ��B�傫�ȉƂ̓��_�������B�Ƃ���u�����Ĕ���A�Q�Ĉ��v�A�����������ł���J�I������Ώ㓙�Ƃ���S�����͂Ȃ��Ȃ����グ�����̂ł͂���܂����B����Ɏd���͎Љ�I���l��n������̂ł��邩��A���ߐl�����Ƃɐ���Ȃ��邱�Ƃ����łƝ�������̂͂܂���������ł���B�d���ɉ��l������̂����璆�ł���قǐ���Ȃ���̂͌��グ�������ł���B�u�ΘJ���v�u�҂��ɒǂ����n�R�Ȃ��v�Ƃ������t������B
�@�Ƃ���ŁA�ŋ߂͂����������͋C���Ⴄ�̂���Ȃ��낤���B�m���Ɂu�����ԓ����v���Ƃ��b��ɂȂ邯��ǁA����ɂ��Ắu�F���悭�����v�Ƃ����悤�Ȕ����������Ƃ��Ȃ��B�����ł�����Ă�����{�l���݈��ɘb���Ɓu����ΕׂƂ������t�͒����l�̂��߂ɂ���v�Ƃ��������B�ق��20�N���炢�O�܂ł́u�����l�͓����Ȃ��v�Ƃڂ₭�l�����������B�ނ�͎c�Ƃ�x���o�͂�肽����Ȃ��B�d�����I���������ŋA��B�^���݈���������ƂȂ������Ă݂�ƁA�}���Ő��w�Z�֒ʂ��Ă�����B�u��w���Ƃ��Ă���̂ɂȂ�Ő��w�Z�֍s���̂��H�v�Ɛq�˂���A�u�V�����X�L����g�ɂ���v�ƌ���ꂽ�������B�Ȃ�قǒ����ԓ������ƂƋΕׂƂ͕K��������v���Ȃ��B
�ΕׂȐ�l�E��{�����Y
�@�킪���{�l�̋Εׂ̌��{�͓�{�����Y�i�����j�ł���B������S���R���i���c���s�j1787�N���܂�B���N����V���̑�Q�[�i1788�`1795�j�ő����̉쎀�҂��o���������B�_�ƋZ�p�͖��n�ł���B�S���I�ɒn�k���Q�������A�����ꂩ��Ꝅ�A���U�Ȃǂ������������Ă����B�_�������͐h���B�����Ȃ����m�K�����ΘJ������Ă��N���{�C�ɂȂ�킯���Ȃ��B���ł��嗬�s����B�n���������I�ޔp�������炵�Ă����̂ł�����B
�@�����Y�͐e���S���Ȃ�16�Ŕ����̂��Ƃɐg�����B���w�S��������͎u��w�v��ǂށB�Ƃ��낪�����Ɂu���̋M�d�ȓ������g���ȁv�Ǝ�����B����ł͂Ƌn�ɍ؎����Ė�������āA���O�̓����œǏ����Ă���Ƃ܂��������u����Ȃ̂����炨�O�̎��Ԃ͉��̂��̂��v�ƌ����B�����œǏ����Ԃ��Ȃd���ɏ[�ĂāA�d���W�߂ɂ����R���̉����œǏ������Ƃ����B���ď��w�Z�̍Z��ɂ����������Y���͂��̑}�b���ے����Ă���B�����ɖ�����肪�~�肩���낤�Ɓu�L���Ȃ��v�B
�@�₪�ēƗ��A����ח�A���܂蓭���A���ӂ̐l�X�̔_�Ƃ����������邤���ɓĎu�ƂƂ��ėL���ɂȂ�B�����������ď��c���ˎ�͂��ߔޕ����Ȃ��̔˂���_���Č��̈˗������āA������10�l�̑喼�i�ˁj���������B�����Y�̃R���T���^���g�Ƃ͂܂������������A�_���Ɛ������߂�����炵�Ԃ���݂�����ώ@���āA�_���̐M�����l�����Ă���₨��w���ɓ���B�n���͎��͂ʼn���������Ƃ������j����т��Č��������B���쑺�i�Ȗ،��j�Č��ɂ�10�N��v�����B���搂�͘J������B�����͎��f���̂��́A����ɓw�߁A�����͓Ԃł����������ȁB
�@�܂��A����ȂƂ��낪���{�l�̂���܂ق����p�A�u�ΘJ���v�A���Ƃ̂��߂ɑP�트������Ƃ����킯�ŁA��O�͍��Ǝ�`�̏ے��ɂ���Ă��܂����B�������O����̕��X�ɂ͋����Y�̈�ۂ͋ΘJ���̉�������Ɍ����Ă��܂��B�������A�����Y���̐l�͂ǂ��܂ł����h�ł���B
�@���Ƃ��ΓV�ۂ̑�Q�[�i1836�j�ŁA�����Y�͍]�ˋl�߂̏��c���ˎ傩��ˋ~�ς�S�ʓI�Ɉ˗������B�Ƃ��낪�ƘV�ȉ��m���N����l�̓����͖F�����Ȃ��B���̂Ƃ��S�ˎm�ɑ��Ă����Ȃ����u�b���L���ł���B���킭�u�����Q�[���}���ĐH�ו����Ȃ��B���̐ӔC�͎��R�̂����ł͂Ȃ����҂̐ӔC�ł���B���R�̂����ɂ���̂ł���Ή쎀����݂̂ł���B�����ł��Ȃ��̂ł���Ύ��҂͂��̍߂�w�����ĐH��f�����玀���ׂ��ł���B�܂���l�����˂A�_���͎������������ʂ̂����R���Ǝv���ł��낤�B��������Ύ������ꂸ���R�Ɠ������Ƃ���̂��B�v�˂̑����J���ėƐH��_�������ɓn���̂��a���Ă����ƘV�ȉ��ꌾ���Ȃ��]�����Ƃ����B����A�����Ўq�̐��ł���B�Ўq�͐m�p���`���Ȃ��͎̂w���҂̂䂦�ł���Ɛ����������l�ł���B�Ўq�ƈ���ċ����Y����͎��H���Ă����̂����甗�͂��Ⴄ�B
�V�E�̂��߂̋ΘJ���
�@�����Y�͂Ȃ�Ƃ����Ă��_���̃X�[�p�[�X�^�[�ł���B�u���k�J�ǁv�Ƃ������t������B���ꂽ���͔����k���A�J�̓��͏��ւŏ����ɐe���ށB�c���ɊՋ����I�X���K�̕�炵�����邱�Ƃō������ތ�̓���̃X�^�C���Ƃ��Ă悭�����B
�@�����̃N�u�`�����ŐA�ъ����ɍ�����������ꂽ�̉��R���l�搶�͎Ⴋ���닞�s��w�_�w���Ŋw�ꂽ���A���t����u�S���Ƃ������͉̂J���~�낤�Ɨ������悤�ƈ�N365���x�݂͂Ȃ��̂��B���̌��ӂ�����Δ_�w���ɓ���v�Ɣ��j��������ꂽ�������B
�@�Ȃ�قǂ����Ȃ�d���ł��낤�Ƃ��A�����V�E���ƐS���ē������߂悤�Ƃ���A���̂悤�ȐS�\�����K�v�Ȃ̂ł��낤�B���R�搶�͂ǂ��֍s���ɂ���ƕ��p�Œʂ��ꂽ�B��ݔ_��Ȃ̂ł������B�u���������������Ƃ����ł�90���Ă���ꂽ�B���f�N�X�A�_�|�����A�킹�A�������A�ǔ��͂̍u���ł������B
�@���̓���A�푈���E���͒��挧�̍����n�тŔ_�Y������Ă錤���ɖv�����ꂽ�B������p���낭�����ۂȂ��A���߂��A���i���遁�{���j�ɋ߂��A�Q���Ă���F���~��������S�ł�����Ă�����̂ɁA���̘͂A���́u���n�ɍ앨���ł���킯�͂Ȃ��B�C���ӂ�Ă���̂ƈႤ���v�ƉA����@���Ă����B�������搶�͂���Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��悩�����B
�@�b���k�邪�A�]�ˎ���ɂ͋{�����i1623�`1697�j�Ƃ����l�������B�L���ɐ��܂�A�������c�˂�200�̘\��H��ł������A�������V���ČØV��q�˕����_�Ƃ̕��@�����A40�N���₵�āu�_�ƑS���v�i1697�j�����B����͍]�ˎ��㒆���������ɓn���ē��{���œǂ܂ꂽ���̂ŁA�_�ƋZ�p���v�ɂ������ɍv�������̂ł���B�u�_���͔_�ƋZ�p�ɏڂ����Ȃ�����A�͂�s�����Ĕ_�Ƃɋ���ł��Ȃ��Ȃ����v�������Ȃ��ǂ��납��������E�����Ȃ��B�_�Ƃ̖��Ɉ�̏����ɂł��Ȃ�Ǝv���_�@���������Ē������B�v�Ɩ}��ɏ����Ă���B�ނ����j�����͎̂R�z������ߋE�A�ɐ��A�I�B�̏����ɓn��B����Ɏ����Ŕ_�ƂɌg��肻�̌������܂Ƃߏグ���̂ł���B����܂Ŕ_�Ɩ{�͂킪���ɂ͑��݂����A���߂ɒ����̏��Ђ̌������d�˂��������B���삪���ɏo���N�A�{����傳��͔ޕ��֗����B�܂��������C�t���[�N�B�u�_�ƑS���v���������߂̐l���������B
�@���M���ׂ��͂����ɏЉ���O�l�̑씲������B�͎����̒n�ʂ▼�_�A�܂��Ėׂ���`�̂��߂Ɋ������ꂽ�̂ł͂Ȃ������B�Ђ�����l�X�̍������~���A���̐����̎��͍X��������Ċ������ꂽ�̂ł���B�V�E�A���C�t���[�N�Ƃ������ɂӂ��킵���������ł���B�u�ΘJ���v�Ƃ͐��̂��ߐl�̂��߁A�����ĉ����������̓V�E���Ƃ�������Ȉӎ����K�v�Ȃ̂ł͂���܂����B
�@�����̐�B�Ɍ��炸�A�����̂����͉ߋ��̈�Y�̏�ɐ����Ă���B�ˏo���Ė��O���c���Ă��Ȃ��Ă��A���Ƃ��Δs���̓��{���Č����Ă���ꂽ��y�����͂܂��Ƃɂ悭�����ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B���̃G�l���M�[���܂��R�������Ă���60�N��ɎЉ�l�ɂȂ������́A����Γ���㐢��̈�����ł͂Ȃ��������낤���B�ڂ݂���������Ȃ炸�p���������B�������A����͕n�����䂦����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł����āA����Ɍo�ρE�Љ�Č�����Ă��āA�o�ϑ卑�ƌ�����悤�ɂȂ茋�\�ȕ�炵���ł���悤�ɂȂ����̂�����A�����a�݂����Ȑl���𑗂�Ȃ��Ă��߂���ɂ��������Ƃ͂Ȃ��B
�����ԘJ���͋C�̔������r�[���H
�@���炭�O����A�s�����J�����������Ă���B���c�Ǝ҂Ȃ炢���m�炸�A���ߐl�ł��邩��s�����J��������͍̂����I�s���ł͂Ȃ��B��������Ɍ������ĕ�V�������Ƃ�̂����R�ł���B
�@�s�����J������������悤�ɂȂ����̂͂ǂ����o�u�������A1990�N��㔼����ł��낤�B���̈ȑO�A�s�����J�����[���ł͂Ȃ��������A�s�����J�����Ă��u����Ă��v�ƌ�������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B���͕s�����U�����Ă���Ƃ��A����ɑ���S�}���肾�ƌ�����̂����ł���������A�Ђ�����Ɖ��������ɂ�������̂��B�Ƃ��낪�����ł͂���Ă��Ȃ��ق����������Ƃ������炢�ł���B
�@�u���̂��߂ɓ����̂ł����v�Ɩ₦�Α�T�́u�����̗Ƃ̂��߂ł���v�Ɖ���B�����̗Ƃ̂��߂ɓ����Ƃ����̂͋ɂ߂ē��R�A�����I�ł���A�d���̖ړI�͗��ȓI�ł����āA��Ђ⑼�l�̂��߂Ɋ��������̂ł͂Ȃ��B���ہA1970�N�キ�炢�܂ł͂�����u�����c�Ɓv�����������B�Ȃɂ��남�ߐl�������铹�͉�Ђœ��������Ȃ��̂�����A������x�c�Ƃ������Ƃ����C�����͗����ł���B�g�����c�ƋK�����悤�Ƃ���ƁA�g�������u�c�Ƃ�点��v�ƕ���������悤�ȏ�ʂ����Ȃ��Ȃ������B�Ƃ��낪�����ł͎c�Ƃ͂��Ă��邪��V�������Ȃ��̂ł���B
�@�܂萶���c�Ƃł͂Ȃ��B��H���̐l�̂��߂��A�ڋq�̂��߂��A���R�͂Ƃ������s�����J���Ƃ͗����I�s���ł���B�����ȊO�̒N���̂��߂ɕ������Ă�����̂ł���B�������L���x�ɂ͎��Ȃ��B�\�ʓI�Ɍ���ΐ̂́u�ΘJ���v�I���l�ς��f�i���邵�A�����I�s���ł��邩�炢���ɂ��u���̂��߁A���l�̂��߁v�Ȃ̂ł���B�܂�u�����̗Ƃ̂��߂ɓ����v�ƌ����A���́u�����̗Ƃ̂��߂ł͂Ȃ��v�Ƃ����s�v�c�Ȍi�F�Ȃ̂ł���B
�@�Ƃ��낪�O�q�̂悤�ɒ����œ����Ă��钓�݈������̖ڂɉf����{�����̓������́A�ƂĂ��Εׂɂ͌����Ȃ��ƌ�����B������肩�ނ�́u�ł��邱�ƂȂ���{�ɋA�肽���Ȃ��v�Ƃ܂Ō����̂ł���B���R�́A�N�ɐ���̖{�Ђ̉�c�ɏo�Ȃ���ƁA��c�����ɂ��炯�Ă��āA�u�������v�u�悵�A��낤���v�Ƃ������͋C���Ȃ��Ƌ�肫���Ă�����B�����œ����Ă��钲�q�ł���ׂ�Ɠ��������Łu���O�A�Ȃ�ł���Ȃɒ����������Ă���́v�ȂǂƔ��܂���������B�ނ�̖ڂɂ͗v����ɍ����́u���C���Ȃ��v�Ɖf��B���X�N�͂��邪�������ӂ̂܂܂ɘr���钆���̎d���̂ق��ɂ�肪����������͓̂��R���Ƃ��������B�������Ƃ��ł���B
�}�l�W�����g�̎��_����
�@�J����@��32���i�J�����ԁj�ɂ��u�g�p�҂́A�J���҂ɁA�x�e���Ԃ�������T�Ԃɂ���40���Ԃ��āA�J�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�A�g�p�҂́A��T�Ԃ̊e���ɂ��ẮA�J���҂ɁA�x�e���Ԃ���������ɂ���8���Ԃ��āA�J�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v�Ə����Ă���B
�@���ꂪ���@��36���i���ԊO�y�ыx���̘J���j�ɂ���āA�u�J���ҁi�g���j�Ə��ʂɂ�鋦�������ΘJ�����ԉ����A�x���J�������邱�Ƃ��ł���B�v���ƂɂȂ����B1947�N�ɘJ����@�����������Ƃ��ɂ͉���I�ȘJ���@���Ƃ��ꂽ���A1949�N�ɂ�����O�Z����ɂ���Ď��R�Ɏc�Ƃ�����悤�ɂ����̂ł���B
�@8���Ԃƌ����Έ���̎O���̈�A�������Ԃ�8���ԂƂ���Ύc���8���ԁA�펯�I�ɂ͎c�Ƃ͐������ԂɐH�����݁A�ʂĂ͐������ԂɐH�����ނ��ƂɂȂ�̂�����A����8���ԘJ���̈Ӗ��͌����Čy���͂Ȃ��̂ł���B������g�������ɂ����Ă͂����Ƃ���{�I�ȘJ�������Ƃ���8���ԘJ�����Ɉ���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����������͐��̋Q���������ł�����A��ЍČ����s���ł���A���͂��ׂ��Ƃ���͋��͂��˂Ȃ�Ȃ��B������O�Z����ɂ��ẮA������������ɌJ��Ԃ��Ă����̂ł���B
�@�����ł͖@�����߂͉��֒u���āA�u�����߂��v�̎��ӂ��l���Ă݂悤�B
�@�T���ē����߂��Ƃ����ꍇ�A�J�����Ԃ̒����A�܂莞�ԗʂɒ��ڂ��邱�Ƃ������B�������A�Y��ĂȂ�Ȃ��̂͘J�����Ԃ̎��A�J�����x�̖��ł���B�l�Ԃ͂��ꂼ����I�ł���B�Z�������������ӂȐl������Β����������Ńp���[������l������͓̂��R�ł���B�J�����x��������Ƒ��肵�Č��߂Ȃ�����A�P���ɘJ�����ԗʂ����߂Ă��������ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�@�n�D�����炷��Έ�C�萬�ɏW�����Ďd�����������^�C�v�����邵�A���킶��Ǝ��Ԃ�������^�C�v������B�@�B���g���ē������ƘJ���Ȃǂ͎d���ɕK�v�Ȏ��Ԃ𑪒肵�₷������A���Ă͍�ƌ����Ȃǂ�ʂ��ĕW����Ǝ��Ԃ����肵�A����Ǝ��ԗʂŎd���̐��ʂ𑪒肵���̂ł��邪�A�ŋ߂͂�����z���C�g�J���[�I�E�킪��������e�Ղɑ���ł��Ȃ��B
�@�Ƃ��������قƂ�ǂ��̂悤�ȉȊw�I�Ȕ��z�E�{�����Ȃ��B���܂��Ƀ}�l�W�����g�s�݂ƈ����������邭�炢�E��̊Ǘ����ł��Ă��Ȃ��B�ٗʘJ�����x�Ƃ��A�z���C�g�J���[�E�G�O�[���v�V�����iwhite color exemption�j�Ȃǂ͖{�l�̎�̐��d����Ƃ����ȑO�ɁA�Ǘ��̕����ƌ����������Ȃ���Ԃł���B
�@�����̎��ԊǗ��̂ł��Ȃ��Ǘ��҂Ƃ����͉̂ʂ����ĊǗ��҂ƌ�����̂��ǂ����A�g���Ȃ炸�Ƃ��o�c���ɂ����Đ^�ʖڂɂ��l���ɂȂ邱�Ƃ��厖�ł��낤�B�������X�̎��ԊǗ����ł������āA���������ǂ����Čo�c�v��𗧈ĂȂ���̂��B���łɌo�c�̑̍ق��Ȃ��Ă��Ȃ��ƌ����ׂ��ł͂���܂����B
�@�����d�������Ă���`����E�a������Ɖ��肷��B�`����͎d����8���ԂŕЕt����B�a�����10���ԕK�v�Ƃ���B�J���͒̎��Ԃ͂a���Ԓ����B�ԕ��c�Ǝ蓖�����B�����d�������Ă���̂Ɏ����i��Ђ��炷��Ύx�����j�͂a����̂ق��������B�u�J���ʁ��J���͂̎��~�J�����ԁv�̌����ɓ��Ă͂߂�`����E�a����͓�����V�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�@��l�̒�����1,000�~�Ƃ���B�`�����8���Ԃ�8,000�~�B�a�����10���Ԃ�10,500�~�i8,000�~�{1,000�~�~1.25�~2���ԁj�ƂȂ�A���̒i�K�ŁA�������`�����1,000�~�����A�a�����1,050�~�ɂȂ�B�J���ʂ��������̂ɒ������z������������Ă���B����J�����������ɖ��炩�ɔ����Ă���B
�@���͂��ꂾ���Ɏ~�܂�Ȃ��B�d�����I�����`���������ƋA��Ď����̗]�Ɏ��Ԃ����R�Ɋy���߂�Ƃ������͋C�͊T���ĉ�ЎЉ�ɂ͂Ȃ��B�u�����͋��������Ȃ��v�Ȃǂƌ����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B��������Ƃ`�����10���ԓ������ƂɂȂ�B���R�Ȃ���`�����8���ԕ��̎d�����x��10���ԕ��̂���Ƃ͈قȂ�B�����Ȃ�ΏW���͂��ቺ����͔̂������Ȃ��B
�@�������Đ��͒Ⴋ�ɗ����B�c�Ƃ��P�퉻���Ă����Ђɂ����ẮA�J�����x��������X���ɂ���͕̂K�R�I�Ȃ̂ł���B���ʎ�`�Ƃ����Ă��A�J���̎��ɂ��ċK��ł��Ȃ��܂܂Ɍ��ʂ��������߂�悤�Ȏ��Ԃł���قƂ�LjӖ����Ȃ��B����ȏ�ԂŁA�W���I�ɖ{�C�Ŏd��������悤�ɂȂ�ł��낤���B
�@���̈Ӑ}�͗v����ɁA�c�Ǝ蓖���o�������Ȃ��̂ł��낤�B�c�Ǝ蓖���o���a��A���ʎ�`�ŃP�c��@���ĂȂ�Ƃ��������Ƃ����{�������������ł���B����Ȃ��Ƃ�����ƌ��ǁA���炾�玞�ԏ����^�̘J���ɂȂ邾���ł����āA��Ђ̊������Ƃ͋t�ł���B
�@���̂悤�ɍl����ΘJ�����Ԃ��������Ƃ��K�����������߂��Ƃ͌����Ȃ��Ƃ������_�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��낤���B
���l�͎d����V��
�@�`����E�a����̎���͗D�G�Ȑl�Ƃ����łȂ��l�Ƃ������Ĕ�r�ΏƂ����̂ł��邪�A����ł̋����Y��������̂��܂��ے�ł��Ȃ��B���̂��Ă̐E��ɂ́u�S�v�ƈؕ|��������h�������X������ꂽ�B�u����Ȃ��Ɠ���ł��Ȃ���v�ƊF�������グ����v�ٍl���ĉ������鐦�r�̐E�l�����Ȃ��炸����ꂽ�B�ނ�͐l�ԓI�ɂ����͓I�ł������B������l�C���������B
�@�E��Ŗ��͓I�ȕ��X�́u����͎����̎d�����v�Ƃ����ӎu���m�ۂ��Ă���ꂽ�B��Ђ̂��߂ɓ����Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ȏq�̂��߂ɓ����Ă���̂ł��Ȃ��B���t�ł͌���Ȃ����d���͔ނ�ɂƂ��Ďg���imission�j�Ȃ̂ł���B�����炤�܂������Ȃ��A�ʔ����Ȃ��ȂǂƂ��Ď������K���Ɉz����Ȃ�Ă��Ƃ��Ȃ��B�����Ȃ���ΐH���Ȃ��͎̂����ł��邪�A�ނ�̔]���Ɂu������������Ȃ��v�Ƃ����ӎ��͂Ȃ��B�u��������Ă���v�̂ł��Ȃ��B�B��u�����v���u�����Ă���v�̂ł���B
�@�ނ�͊m���ɒB�����̖��͂ɂƂ�߂���Ă���悤�ł��������B�B���������߂ē����ƂȂ�ΒN������Ă��e�Ղɂł���d���ł͂Ȃ��A�u����������v�ƌւ����̂������Ɍ��܂��Ă���B�u���v�Ȃ̂ł���B�ӋC�n������̂ł���B
�@�����Č����A�ނ�͎d����V��ł���B���̃{�X�͐l�H�q���𐧍삳�ꂽ�B�u�������Ƃ������ɂȂ�̂ł��ˁB���������ǂ��������]�Ȃ�ł����H�v�B�{�X�͌���ꂽ�B�u�l�H�q�����v�����f����������ŁB�v���ނނށB�Ȃ�قǃv�����f���V�т̍D���Ȑl�ł���A�ߋ��Ȃ��Ė{���̐l�H�q���̂ق����u�n�肪���v������Ɍ��܂��Ă���B�{���̃v���͎d����V��ł�����炵���B�ӖځB��Ǝ��v�����˂�ƌ������t�����邪�A�d����V�ԗ͂�����A�܂������u���v�Ǝ�����˂�v���Ă��ƂɂȂ�܂��˂��B���ɂƂ��Ă��̌��t�͕s�ł̋P���������Ă���B
�@�����Ƃ��V��ł���̂ɂ���蕨�Ɖ��蕨������B�Ђ���Ƃ���ƈ��|�I�����̓G�Z��������Ȃ��B���킭�A�d����V�Ԃ̂ł͂Ȃ��āA��ЂŗV�ԂƂ����荇���ł���B�V��ł���̂�����Z���l���̎��Ԃ����茸�炵�ē����Ă��Ă���V���C�ɂȂ�Ȃ��B�G�Z��������Ɖ�Ђ����邪�A���̎Ј����������ɖ��f�������ނ�B�ȂE��ؗ����Ԃ������B�d���̎�������A�܂葼�̐l�Ɠ������̎d�������Ă���ƍl����A�����ؗ����Ă���z�̊o�����߂ł����Ȃ�͓̂��R������ł���B
�����ԘJ���͈�@�ł���
�@�������͏A�ƋK���Ɋ�Â��̂ł��邪�A�A�ƋK���̓��e�Ɖ^�p�͘J����@�A�J������Ɉᔽ���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂�g�����͓������ɂ����Ă͖@���ƒc�̓I�J�g�W�ɂ���Ď���Ă���͂��ł���B�T�[�r�X�J���Ȃǂ����ɂȂ邪�A�@���E����ᔽ�݂̂Ȃ炸�A�A�ƋK���ᔽ�ł�����B�܂����A�ƋK���ŃT�[�r�X�J�����K�肵�Ă����Ђ͂Ȃ��͂����B�d�����I����Ă��܂ł���Ђɑؗ����邱�Ƃ͋ւ����Ă���B�����A��c�Ƃ��A��Ђ̏��ނ��O���Ɏ����o���͖̂ړI�̔@�����킸�{���֎~�����ł���B
�@�u�������ʂɂ���Ȃ��A���͂��̌������������̂��B�d�����D���Ȃ�������Ă����Ăق����B�v�\�\���ԊO�J���K���O�Ŏ��R�ɓ��������Ƃ��������]���҂������B�Ȃ�قǐS�����Ƃ��Ă͌��グ�����̂��ƌ��������̂ł��邪�A���ꂪ�\�֏o��Ώ�i�͊ēs�s���͂��ŊԈႢ�Ȃ����������B�����͓��ʂ��Ƃ��ďA�ƋK���ᔽ�����F����A�₪�đ��̏]�ƈ����A�ƋK���ᔽ�R�Ƃ����Ȃ��悤�ɂȂ��Ă����傪�����Ȃ��B
�@�g���Ƃ��Ă��c�̓I�J�g�W�������������g������َ��ł��Ȃ����A�g���K��������ł���B�{�l�͒N�ɂ������f�����Ă��Ȃ��ƒP���ɍl����̂ł��邪�A�g�D�œ����ԓx�ł͂Ȃ��B���Y�W�Q�ł͂Ȃ��A��Ђ̂��߂ɂ��Ȃ��Ă���̂��Ƃ��������S�����炿�炷��̂ł��邪�A�]�l���Ȃ��đւ���d�������Ă���悤�Ȑl�ł���A��g��������̒����������ł���B�������o�c���Ƃ��Ă͂���قǔނ̎d���Ɏ��S���Ă��Ȃ����̂�����A��g����������Ă��Ă܂ŔނɎd�����������Ƃ͍l���Ȃ��B
�@���ԊO����͐̂����S�S�邵���̂ł���B�Ƃ��ɎJ�����ƂȂǂł́A�J���̋�S�A�����Ȕ[�����d�Ȃ��Ē����Ԏc�Ƃ������Ȃ�B�u�Ƃɂ�����邵���Ȃ��I�v�\�\�̂ł͂��邪�A�l���Ă݂���ׂĂ̎d�����Ƃɂ�����邵���Ȃ��̂ł����āA�����I�ɂ͎d���̂����A�J�����Ԃɂ��Ă͓��ስ�����Ȃ��Ƃ�����������Ȃ���ی����Ȃ��Ȃ�B
�@�c�ƂƂ����̂́A8���ԘJ���ȏ�ɘJ���\�Ȏ��Ԃ�����Ƃ����v�����݂ɂ��̂ł���B�����̎d���͍����I�邵���Ȃ��B����24���ԘJ�����Ƃ���A�c�Ǝ��Ԃ́i�����́j�Ȃ��̂ł����āA�c�ƂƂ͗v����ɖ����̘J�����Ԃ̐�H���Ȃ̂ł���B
|