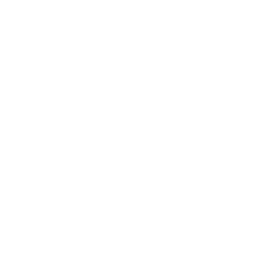
 ライフビジョン学会では3/26(土)公開学習会「働く側からみた日本経済総括」を行いました。 ライフビジョン学会では3/26(土)公開学習会「働く側からみた日本経済総括」を行いました。
問題提起講演とコーディネータ
奥井禮喜
(有)ライフビジョン代表
【農業の衰退】
① 農林水産業生産
国内純生産比が1955年23%
→1975年5%
② 第一次産業人口
1960年 1,439万人・32.7%
1980年 606万人・10.9%
③ 食用農産物自給率
1960年82%→1979年33% |
|
経済ジャーナリスト・師岡武男氏ご提供の
「自分史的覚書」への感想的まとめの第二弾
高度経済成長について
いまでは高度経済成長といってもピンとこない人々が現役で活動しておられる。とはいうものの、戦後の日本経済を考えるために高度経済成長を無視することはできない。よくもわるくも、それが今日の日本経済の基盤を作った。
師岡さんは、「経済成長によって国民の生産物や所得の総量が増加する。後に『くたばれGNP』(国民総生産、現在はGDP・国内総生産を使う)というような批判が出たけれども、貧しかった日本にとって、まず生産物と所得の増加が必要なのだから、基本的に支持した」と回顧されている。同時に、「経済が高成長でも『いい国』になったという実感はなかった」とも。
これ、後輩のわたしも全面的に共感する。後に戦争の廃墟から「フェニックスのごとく立ち上がった」などと形容されたけれども、実際その渦中にあって、高度経済成長に感謝した記憶はない。というよりも、日々の仕事に追われ、また企業間過当競争、経済成長至上主義に対する批判が強かった。産業戦士というような言葉が幅を利かせてもいたから、これらに対する批判が「くたばれGNP」を支持した大衆的気風である。
高度経済成長は1954年後半から1974年までの20年間をいう。
この間GNPは年率10%である。消費者物価は年5~6%常に上昇した。経済政策は、輸出促進・内需喚起(国債発行が体質化する)に重点が置かれた。重化学工業を中心に高度成長、規模の拡大+集中。大コンビナート建設と企業合併が目立った。1ドル=360円、石油1バレル=2ドル以下であった。
設備投資主導の経済成長で、とくに1960年代、銀行は常にオーバーローン、大企業が農協にまで借金を申し込んだような事情であった。個人消費支出は、1960年~64年が国民総支出の57.9%であったが、経済成長が続くほどに下降して、75年~79年には53.8%になった。所得の1/4が貯蓄に回された。人々の脳裏から生活不安が消えたことはほとんどない。
正確にいうならば高度経済成長とは大企業の高度成長である。
巨大企業の集団支配体制が確立し、中小企業の下請け化が深化し、日本経済の二重構造が固定化して格差が拡大する一方である。中小企業の賃金は大企業の80%程度である。
「安かろう、悪かろう」と顰蹙買った日本製品はどんどん性能が向上し、今度は「英国が創造し、米国が応用し、日本が企業化する」と皮肉をいわれた。1959年に対米貿易収支が黒字化、63年にGATT11条国、64年IMF8条国、そしてOECD加盟を果たし、唯一アジアの先進国となった。68年にはGNPが西ドイツを超えて米国に次ぐ世界第2位の経済大国になった。
都市人口は1945年に28%だったが、70年には72%になる。62年に東京が世界初の1000万都市になる。ドーナツ化・ベッドタウンなどの和製英語が作られた。耐久消費財は三種の神器(電気洗濯機・電気冷蔵庫・白黒テレビ)から3C(カー・クーラー・カラーテレビ)へと移る。
チェーンストア、スーパーマーケットが華々しく登場し「消費革命」などと呼んだ。一言でいえば、生活の米国風化が進んだ。「消費者は王さま」だという気風である。ちゃちな王さまではあったが。後に、ダイエーの中内功(1922~2005)は「早くいえば使い捨て文化をめざした」と語った。
農林水産業は、国内純生産費が1955年全体の23%であったが、75年には5%になった。第一次産業人口は、1960年1,439万人(全体の32.7%)が1980年は606万人(同10.9%)に落ちた。
食用農産物自給率は、1960年82%であるが79年に33%に低下した。コメは過剰、麦・穀物飼料は極端に輸入依存。野菜・果実・鶏卵・牛乳・肉類はほぼ自給していた。耕地面積がどんどん減少した。農業の副業化が進んだ。自立経営農家は79年に全農家戸数の7.4%である。昨今、農業の六次産業化などが唱えられるが、営々と! 農業を衰退させてきたのである。
重要な問題は公害(public nuisance・公共の迷惑/pollution・汚染)だ。
世間の注目を集めるようになったのは1964年前後だが、明治時代の足尾銅山鉱毒事件(1890年社会問題化)以来、国の公害対策には力が入っていなかった。儲からない投資であるから企業家が嫌う。企業家が嫌うから保守系政治家も嫌う。官僚もそれに従う。1970年前後は、重金属(水銀・カドミウム・ヒ素)、化学物質(PCBなど)、排ガス・騒音・振動・地盤沈下などなど、日本は公害列島であるというにふさわしかった。
大阪市は大正時代に大気汚染対策を開始した。しかし、昭和の戦時体制に入り、国策によって中止させられた。戦後、大阪市のスモッグは1956年から60年に、年間125日を数えた。石炭から石油に変わったら今度は高濃度の亜硫酸ガスに苦しめられた。
1955年、福岡県は公害防止条例を作った。福岡県経営者協会が反対し、九州大学が大気汚染観測のために設置した観測器すべてが破壊される事件が発生した(犯人不明)。協力要請に出向いた県職員に八幡製鉄幹部が「街は八幡でもっているのだから煙が嫌だという不心得市民は出て行ってくれ」とはねつけた話が残る。毒を食らえば皿までもというわけだ。
61年、八幡製鉄周辺の住宅地観測によると、煤煙が月平均64トン/㎢が降った。(最高は80トンを超えた)
四大公害事件(水俣病・新潟水俣病・イタイイタイ病・四日市ぜんそく)が有名である。国は問題発生しても容易に取り組まない。
水俣の場合、1957年に新日本窒素の排水による魚介類汚染(有機水銀中毒)を、熊本県が指摘して排水停止をおこなおうとした際、国は県の介入を阻止した。国が新日本窒素の責任と認めたのは68年である。
厚生族のドンといわれた橋本龍太郎厚相(1937~2006)が、水俣病患者との交渉で「人命軽視だ」と抗議された。橋本は「政府が人命を大事にしなかったことがあるか」と猛反撃した。いかに売り言葉に買い言葉だとしても、前後の関係をみれば人命軽視は明明白白である。この発言は非常に意味がある。
公害14法を成立させ、衆議院が環境を守る決議をしたのは1970年12月9日であった。第64臨時国会は「公害国会」といわれた。
まことに紆余曲折というか、人命優先の政治がなされるには市民の大きな力が必要だということを痛感させられた。
以上は雑駁な高度経済成長の素描に過ぎないが、高度経済成長についてどうしても反省し、申し送りしたいことを簡単に書く。
① いまの人たちはわかりにくいかもしれないが、当時は消費者物価の高騰に常に悩まされた。だから高度経済成長しても生活がラクにならなかった。不況で動きが取れないのは困るが、景気の数字面がよければ万事OKというものでもない。かくして組合はひたすら賃上げに汗をかいた。
しかし、本当に大事なことは日々の生活にきちんと足をつけた生活改善への取り組みであって、経済成長率やベア率だけでは話にならない。
賃金引き上げだけの活動では生活を守られないという事実は、誰もがわかっていたのである。にもかかわらず、国民春闘だとか生活春闘だとか、キャッチコピーが飛んだり跳ねたりしても、本当の生活改善運動がなされなかった。だから、昔の組合は大いに賃上げで奮闘したという年寄りの発言は、あまり自慢できる話ではないのである。
いま、安倍内閣と日銀がひたすらインフレ率2%にこだわるのは、国民は景気がよくなりさえすれば「善政」だと思うだろうという、不埒な目くらまし作戦である。為政者がそのように考えるような体質を作ったのは、国民一般が経済の在り方をきちんと思索してこなかったからである。ここに師岡さんが「対案を考えよう」と提言されている核心があると思う。
② 見てくれの経済さえなんとかなればよろしいという気風が支配するようになったことの意味を再検討しておかねばならない。
なるほど、高度経済成長期間を経て、経済のハード面は、たとえば耐久消費財がすべての家庭に浸透して便利になった。しかし、すでに1980年代に入ると、「豊かさ・ゆとりが感じられない」とか、「豊かさとは何か」という問いかけが日常的になった。Japan as No.1といわれていたにもかかわらず、である。
多くの組合において、「モノから心へ」、「所有から使用へ」、「ハードからソフトへ」「ソフトからハートへ」というようなキャッチコピーが躍ったのも事実である。しかし、それらのコピーが戦略・戦術段階へ下されたかというと、いわば「そのうちなんとかなるだろう」というような気風で、掘り下げた取り組みがなされなかった。当時の組合関係者は重々反省するしかない。
③ 公害問題については、もっと胸が痛む。
組合が企業内活動に止まっている限り、いかに過激に賃金闘争をやろうとも、公害のような社会的問題解決の当事者として組合が登場することはない。実際、1970年前後、公害を垂れ流している企業と組合が連携して、抗議する市民運動と対峙したという苦い事実も残る。
八幡製鉄の事例は決して八幡製鉄だけの問題ではない。企業が大きくなればなるほど、企業意識と企業城下町意識が支配的になる。
公害を生み出す危険性がある事業においては、なによりも第一に、そこで働く労働者が最初の被害者になる。生活の糧を稼ぐのであって、健康や生命の危険に耐えることが目的ではないのである。
原発の場合も同じである。仕事をしている人々は絶対的自信を持っておられるとしても、現実に大きな問題から小さな問題まで、しばしば新聞に報道される。働く人々のなかには、いろいろな意見があるのではなかろうか。この場合、企業内の視点だけで考えるのではなく、少なくとも組合は経営側以上にシビアな労働安全の視点を確立するべきである。それが、結果的にさらなる安全向上に貢献すると思う。
新自由主義(1980~)について
1970年代はスタグフレーション(造語stagflation・不況とインフレが共存)が問題視された。
71年のニクソン声明後、ドルが世界的に垂れ流される。バブル一直線だから偽札よりも性質が悪い。さらに、74年には先進国経済成長は頭を打った。
このような背景で、従来主流だったケインズ(1889~1946)理論の否定的論調が輩出した。ケインズ理論は、財政を有効需要の調整手段として駆使し完全雇用をもたらそうとする。だから不況では赤字公債を活用するのである。これは需要を軸とした経済政策である。
フリードマン(1912~2006)は、これに対して供給を軸とした経済政策を主唱した。財政は均衡予算主義(赤字を出さない)である。そのために、企業の経済的自由を拡大して、安上がりの政府(cheap government)をめざす。これは実は古典派への復古主義である。
大きな政府となったのは、日本においては1960年代、公害や都市問題などが大きくなり、これを市場の欠陥と呼んだ。市場の欠陥を私企業に委ねていても解決しないので、公共の積極的介入によって問題解決しようとしたからである。これが公共経済学である。
大きな政府が必要になったのは市場が自由に活動した結果である。
福祉国家をめざした結果ではない。いわば、市場経済原理主義による、国民への負担押し付けである。社会資本を福祉ではなく、さまざまの問題処理に投入せざるをえなくなった。
当然ながら安上がりの政府論は実業界には評判がよろしい。重ねて、福祉国家としての負担が国の経済を不合理にするというキャンペーンが大きく展開された。まさに、レッセ・フェールの資本主義に戻そうという考え方である。(日本政府も1969年の経済白書では高福祉高負担を掲げていた)
ドルが世界をバブルにし、カジノ経済化している状態では、実物経済が世界経済を動かせないという問題も見落とせない。供給軸の経済というが、もう1つの主役は統御不能になった金融資本主義の深刻な問題である。
フリードマンの熱烈信奉者であるサッチャー首相(1925~2013)が展開したのは、民営化・公共社会サービスの削減・そして組合対策であった。60年代から経済的停滞していた英国は金融街シティを中心に復活した。ただし、貧困・失業問題は拡大して解決できないままだ。
まだ決着がつかないけれども、80年前後から起こった新自由主義という、資本主義草創期への回帰の思想は、本当の問題解決にはならないと思われる。
単純にいえば、新自由主義は供給サイドの自由度を最大拡大し、大企業が儲かればトリクルダウンで、中小零細、一般国民に効能が回るという考え方である。しかし、現実には資本力のある企業(人)が膨大な資金を溜めこみ、一方格差が決定的に拡大している。トランプ旋風にしても、煽ったから人々が騙されているのではなく、社会が不満のルツボと化していることに注目せねばならない。世界的金融バブルに、その本質的原点がある。
純粋に理屈で考えれば、経済が目的ではなく、経済は手段である。人々の生活=需要を軸として考えるのがスジであるが、世界的に政治を牛耳っているのは政財官の結託であり、圧倒的多数の民衆が経済政策をもって立つと言う事情にはとてもならない。師岡さんが対案をもって闘おうと主張される所以である。
わが国が新自由主義路線へ踏み込んだのは中曽根康弘首相時代(在任1982~1987)である。当時、日米貿易摩擦が厳しかったが、わが経済は土地バブル真っただ中で財テクに浮かれていた。
しかし、続く竹下登首相就任(1987)から森善郎首相退陣(2001)までの足掛け15年は、首相が10人、目まぐるしく替わって1人・1.5年の短期政権が続いた。1992年の宮沢喜一首相以後はほぼゼロ成長、1995年兵庫県南部地震など大不運もあったが、日本経済は縮小均衡路線を漂った。すでに1974年が先進国経済成長のピークであり、小手先の金融政策で経済成長を高めるという方針が妥当とは考えられない。
1990年代に入って和製バブルが崩壊した。
96年元旦、読売社説は「政治も経済も八方ふさがり」と書いた。経済大国というが、経済も日没に向かっていた。なぜなら、突破口は技術立国と少子高齢社会にどう対応するかという課題であったが、財界主流は「雇用か賃金か」論を振り回し、成果主義をかざして社員に発破をかけることしかやらなかった。リストラ一本槍だから、当然ながら人々の元気が出るわけがない。
いま、非正規社員が2,038万人・全体の40%、年収200万円以下が1,119万人・全体の24.1%であるが、これの根源を探ると、1999年の小渕内閣(1998~2000)に突き当たる。それまで労働者派遣法は「原則禁止・例外容認」であったが、「原則容認・例外禁止」へ踏み込んだ。小渕死しても、ガタガタの労働環境を花開かせたわけだ。
労働側からすれば、過剰労働が無くならない限り賃金は上昇しない。正規社員が非正規社員に不具合を押し付けて安閑としているのではなく、膨大な非正規社員の存在が非正規社員の痛烈なアンカーになっているに過ぎない。
モノによる経済成長ではなく、人々の生活を充実させる政策、つまり人々の生活の質(Quality of Life)に注目しなければならないのだが、相変わらず供給サイド(企業家)の都合ばかりを考えた政策が展開されている。
1988年度、大企業の内部留保は100兆円、2014年度は、内部留保354.4兆円、手元流動性100兆円あるという。要するに資金があっても使い方がわからない経営者ばかりだといわれても反論できないのではあるまいか。
|